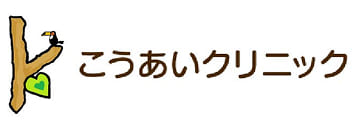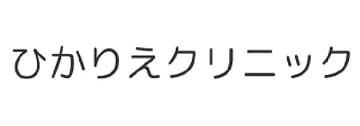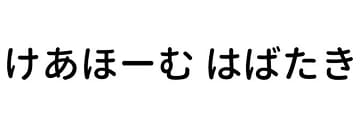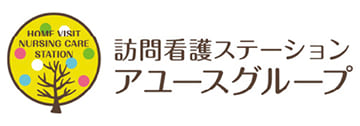Philosophy 理念

魚は水に、
そして人は社会に
人は社会で生きる存在だということを私たちは大切に考えています。
私たちは病院という枠を超えて、地域生活を支える医療を行っています。
医療法人光愛会は創立以来、
開放医療と地域社会との連携を進めてきました。
患者様が地域でいきいきと生活できるように、医療面で直接バックアップするだけでなく、地域の診療所や作業所などとの協力関係を築き上げていきながら、これからも幅広い取り組みを進めていきます。
History 沿革
※1「駅前グループ」とは、光愛病院が患者を退院させアパートで生活できるよう支援する活動を積極的に展開していました。
こうした地域を基盤に、大阪では患者同士が交流する動きが広がっていきます。やがて光愛病院の医師らがアパートを借り上げ、公式に患者が集まり学び合う場が生まれました。
この名もなき集まりが、後の全国患者集会発足へとつながっていきます。
光愛会のはじまり
かつての精神病院は、「鍵の音」に象徴されるように権威主義的で閉鎖的な体制にありました。
病棟は高い壁と鉄格子で覆われ、患者は隔離・収容の対象とされ、そこに本来の医療はほとんど存在していませんでした。
社会復帰を支えるはずの病院が、むしろ病院や職員の都合によって成り立ち、営利追求を優先していたのです。
そうした現実に対して「これは本当に医療と言えるのか」という強い疑念を抱いたことが、光愛病院設立の大きな動機でした。
私は精神医学者としての立場ではなく、一人の精神科臨床医として、人と向き合う姿勢を大切にしてきました。
「医学の水準は研究論文の数ではなく、患者がどう扱われ、どのように治療されるかによって決まる」という信念を胸に、
患者を「病人」としてではなく、一人の人間として尊重することこそ医療の原点であると考えたのです。
そこで私たちは、鉄格子を取り払い、明るく開放的な療養環境を整えました。
力や機械的な方法に頼るのではなく、患者自身が自主性・社会性・責任感を取り戻すことを重視しました。
社会に復帰することを治療の目的とし、その歩みを支えることが、私たちの使命であると確信しています。
「光愛病院―その精神医療のあゆみ―」医療法人光愛会設立時理事長 貴島 千代彦の記載より抜粋
精神病院に長く根強いていた入院中心主義や閉鎖性を乗り越える過程で、病院自体も変化を遂げてきました。
医療従事者が力を合わせ、地域とのつながりを深めながら精神医療の内容を豊かにしていく。
その挑戦の積み重ねが光愛会の歴史であり、これからも揺るがない原点です。
医療法人光愛会
理事長 貴島 千代彦
Office Introduction 事業所紹介
地域活動支援センター、グループホームを運営しています。
-
病院・クリニック
-

光愛病院
- 診療科目
- 精神科・児童思春期精神科・内科・皮膚科
- 所在地
- 〒569-1041 大阪府高槻市奈佐原4-3-1
Google Map - 連絡先
- 072-696-2881
- WEB
- https://www.kouai.or.jp
-

こうあいクリニック
- 診療科目
- 心療内科、精神科、デイケア、訪問診療
- 所在地
- 〒569-1144 大阪府高槻市大畑町6-15 2F
Google Map - 連絡先
- 072-697-1700
- WEB
- https://www.kouai-cl.com
-

ひかりえクリニック
- 診療科目
- 心療内科、精神科、訪問診療
- 所在地
- 〒544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋
2-18-10 88ビル2F
Google Map - 連絡先
- 06-6741-8000
- WEB
- https://hikarie-clinic.com
-
-
地域活動支援センター
-

高槻地域生活支援センター オアシス
地域活動支援センターⅠ型・相談支援
- 所在地
- 〒569-0023 大阪府高槻市松川町25-5
Google Map - 連絡先
- 072-662-8130
- WEB
- https://takatsuki-oasis.org
-
-
グループホーム
-

けあほーむ はばたき
共同生活援助
-
-
訪問看護ステーション
-

アユース高槻
訪問看護サービス
- 所在地
- 〒569-0818 大阪府高槻市桜ケ丘南町23-5
桜ケ丘医療ビル2F
Google Map - 連絡先
- 072-695-7910
- WEB
- https://www.ayouth.jp
-

アユース枚方
訪問看護サービス
- 所在地
- 〒573-1146 大阪府枚方市牧野阪1-12-10
マルエス牧野ビル3F
Google Map - 連絡先
- 072-807-7682
- WEB
- https://www.ayouth.jp
-

アユース森ノ宮
訪問看護サービス
- 所在地
- 〒537-0024 大阪市東成区東小橋1-9-19
玉造駅前ビル3F
Google Map - 連絡先
- 06-4303-3251
- WEB
- https://www.ayouth.jp
-

アユース吹田
訪問看護サービス
- 所在地
- 〒564-0011 大阪府吹田市岸部南1-24-3
アクア
Google Map - 連絡先
- 06-6317-7878
- WEB
- https://www.ayouth.jp
-
Corporate headquarters 法人本部

医療法人光愛会 法人本部
- 所在地
- 〒569-0814 大阪府高槻市富田町3丁目29-13
Google Map - 連絡先
- 072-629-9002
- WEB
- https://